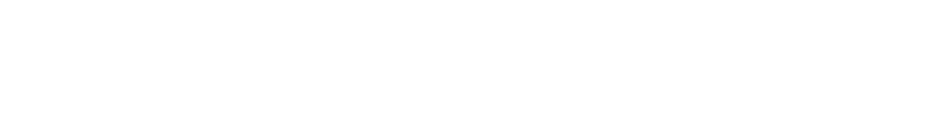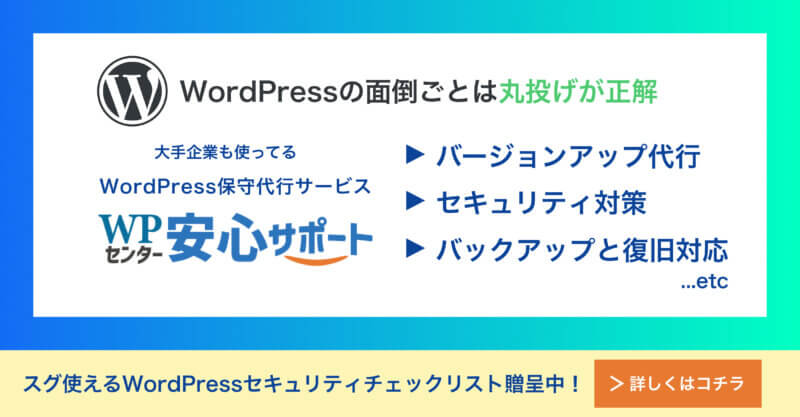中小企業のWebサイト運用担当者にとって、「制作会社にそのまま保守も任せるべきか」「WordPress保守の専門業者に切り替えるべきか」は頭を悩ませる大きな課題です。どちらにも一長一短があり、“費用”“対応速度”“技術深度”など、比較すべきポイントが多岐にわたります。本記事では、両者のメリット・デメリットをフラットに比較し、サイト規模や更新頻度、予算感に応じた最適解を提示します。
制作会社に保守を依頼するメリットとデメリット
結論
制作会社にWordPress保守を依頼すると、一貫した窓口対応とサイト構造への理解が深いため、運用効率は向上します。一方で、専門的な障害対応やセキュリティ運用に関しては、対応スピードやノウハウ面で限界がある場合があります。
理由
一貫対応のメリット:
制作から保守まで同じメンバーで対応するため、サイト設計意図やカスタマイズ履歴を把握した上でメンテナンスを実施できます。WordPress特有のテーマやプラグイン開発背景を理解しているので、改修作業もスムーズです。
デメリット:
多くの制作会社は「納品後の請負対応」を前提としており、24時間体制の監視や脆弱性への即時対策といった専門保守サービスの標準レベルには達していないケースがあります。また、人員リソースが限られるため、他プロジェクトと兼任になることで対応までに時間がかかる場合もあります。
専門保守サービスを選ぶべき理由と注意点
結論
WordPress保守専門業者は、自動監視システムやセキュリティパッチの即時適用など、専門ノウハウを駆使した運用が可能です。ただし、コミュニケーション面で多少の工数が増える点や、コストが高くなる傾向があります。
理由
専門性の高さ:
専門保守サービスは複数サイト運用で蓄積したプラグインごとの障害パターンや脆弱性情報をリアルタイムで共有し、自動スキャン&ワンクリック修正ツールを備えています。これにより、攻撃検知から復旧まで平均2時間以内という迅速対応を実現します。
注意点:
窓口は主にメールや専用ポータルとなるため、サイト制作時の担当者とは別ルートでのやり取りになります。そのため、要件の伝達ミスや見積もり調整に多少のラグが発生する場合があります。また、月額料金は制作会社保守の1.2~1.5倍が相場となるため、予算感のすり合わせが必要です。
コスト・効果の比較:価格だけではない「真のTCO」を考える
結論
単純に初期費用や月額料金を見るだけでなく、ダウンタイムコストや人的工数、トラブル対応時間などを加味した「総保有コスト(TCO)」で比較することが重要です。
理由
直接コスト(初期費用+月額):
制作会社依頼の保守は、初期設定費用込みで月額3万円〜5万円が一般的です。一方、専門保守サービスでは月額4万円〜8万円程度が相場とされ、1.2〜1.5倍程度高くなります。
間接コスト(ダウンタイム+人的工数):
サイトがダウンすると、訪問者数減少や既存顧客の離脱といった金銭的機会損失が発生します。例えば、ECサイト月商1,000万円の場合、1時間のダウンで約13.8万円の機会損失が生じる計算です。また、対応履歴の共有や調査に必要となる担当者の工数も見落とせません。
リスクコスト(セキュリティインシデント対応):
攻撃を受けた際の事後復旧コストや信頼低下による売上減少、場合によっては復元手数料+被害額で数十万円に達するリスクがあります。専門保守ではインシデント前提の自動バックアップ・スナップショット取得を多数並列化しており、被害最小化の観点で有利です。
具体例
ケースA:制作会社保守
- 月額5万円+ダウンタイム(平均年2回/各4時間)
- ECサイト月商800万円 ⇒ 1ダウン×4h=約46万円機会損失 ⇒ 年間約92万円
- 人的工数:トラブル対応に平均8h×2回=16h/月 ⇒ 社内人件費約8万円
年間TCO試算:
5万円×12 + 92万円 + 8万円×12 = 60万円 + 92万円 + 96万円 = 248万円
ケースB:専門保守サービス
- 月額8万円+ダウンタイム(平均年0.5回/各1h)
- ECサイト月商800万円 ⇒ 0.5回×1h=約6.9万円機会損失 ⇒ 年間約6.9万円
- 人的工数:トラブル対応に平均2h×0.5回=1h/月 ⇒ 社内人件費0.5万円
年間TCO試算:
8万円×12 + 6.9万円 + 0.5万円×12 = 96万円 + 6.9万円 + 6万円 = 108.9万円
上記試算からも、総合的コストでは専門保守サービスが約1.8倍のコストパフォーマンスとなることが分かります。
サイト規模・用途別の最適解
結論
サイト規模・更新頻度・ビジネスへの影響度に応じて、依頼先を選ぶべきです。小規模・低頻度更新なら制作会社継続、大規模・高頻度更新やクリティカル用途なら専門保守がおすすめです。
理由
小規模サイト(更新月1回以下、月間PV数~1万):
運用工数が少なく、緊急対応も発生しにくいため、制作会社にそのまま任せることで十分コストを抑えつつ安定運用できます。
中規模サイト(更新月2~5回、月間PV数1万~10万):
更新頻度が上がると、プラグインの競合やテーマのカスタマイズ時にトラブル発生のリスクも増加します。制作会社の保守プランで対応可能なら継続しつつ、監視オプションの追加を検討しましょう。
大規模/クリティカルサイト(更新週1回以上、月間PV10万以上、EC・会員制など):
ビジネスへの影響度が高く、障害や攻撃が直接売上減少に直結します。24時間365日対応・自動スキャン・WAF連携などを備えた専門保守サービスが適しています。
具体例
| サイト規模 | 更新頻度 | 月間PV数 | 推奨依頼先 |
|---|---|---|---|
| 小規模ブログ | 月1回以下 | ~1万 | 制作会社保守 |
| コーポレートサイト | 月2~5回 | 1万~10万 | 制作会社保守+監視オプション |
| ECサイト(中規模) | 週1回以上 | 5万~20万 | 専門保守サービス |
| 会員制サイト | 日2回以上 | 10万以上 | 専門保守サービス(24/365対応) |
導入ワークフロー:切り替え前後の実務チェックリスト
結論
制作会社から専門保守へ切り替える際は、移行計画の策定から引き継ぎ情報の整理、テスト運用、最終切り替えまで体系的に進めることが成功の鍵です。
理由
情報欠落リスク回避:
サイト構成やカスタム設定の引継ぎ漏れがあると、切替時に想定外の障害が発生します。
ステークホルダー調整:
サービス提供元、ドメイン管理者、ホスティング管理者など、関係者間の確認作業を怠ると停止時間が延びる可能性があります。
具体的チェックリスト
- 現状整理フェーズ
- サイトマップ/ページ一覧の最新版を入手
- プラグイン・テーマのバージョン、カスタマイズ箇所のドキュメント化
- ホスティングスペック&DNS情報の確認
- 移行計画フェーズ
- 切替日・時間帯の決定(トラフィックが少ない時間帯推奨)
- バックアップ取得手順の確立とテストリスト作成
- 切替後の検証項目リスト(表示確認/フォーム動作/SSL有効性など)の策定
- テストフェーズ
- ステージング環境での実運用シミュレーション
- テストユーザー招待による動作確認
- 障害発生時のロールバック手順検証
- 本番切替フェーズ
- 本番環境へのスナップショット取得
- DNS切替・キャッシュクリア実施
- 切替後24時間のモニタリング強化
- フォローアップフェーズ
- 切り替え後報告会の開催(主要ステークホルダー対象)
- 初期トラブルレポートの共有と改善計画策定
未来予測:保守サービスのトレンドと5年後のWordPress運用
結論
今後5年で、AI自動化と高度なセキュリティ標準化が保守サービスの必須要件となり、最終的には「自己修復型プラットフォーム」へシフトすると予測されます。
理由
AI自動化の台頭:
機械学習を用いた異常検知エンジンが、過去データ分析から「障害予兆」を検出し、自動でパッチを適用する動きが進行中です。2025年現在でもすでに一部の大手保守業者が提供を開始しています。
セキュリティ標準の高度化:
ヘッドレスCMSの普及やJavaScript SPA化に伴い、サーバー/クライアント両面での脆弱性対策が必須となります。今後はコンテナベースの隔離実行やZero Trust ネットワーク構築が一般化すると予測されます。
具体的動向
- 自己修復型WordPress:
コア・プラグインの変更をバージョン管理+コンテナリストアで瞬時に復旧する機能を持つプラットフォームが登場予定。障害発生時のダウンタイムを実質ゼロに近づけます。 - 統合監視ダッシュボード:
Webサイト運用データやセキュリティログ、パフォーマンスメトリクスをリアルタイム可視化し、AIからのアラートを一元管理。「次世代運用管理ツール」の参入が期待されます。
まとめ
制作会社保守と専門保守サービスにはそれぞれコスト・対応品質・リスク管理の面で明確な違いがあります。小規模サイトならコストを抑えた制作会社保守、中〜大規模かつミッションクリティカルなサイトなら専門保守サービスがおすすめです。今すぐ自社サイトの運用体制を見直し、真のTCOを算出してみましょう。最適な保守パートナー選びが、Webサイトの安定運用とビジネス成長を支えます。